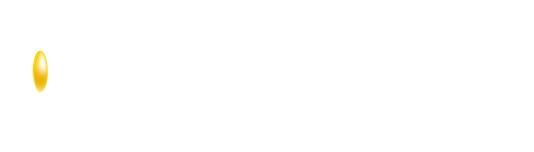Q&A
予約はとれますか?
-
普通の診察は予約制ではありません。病状が変化したとき気軽に受診できることが大事だからです。
混雑して待ち時間が長くなることもありますがお許し下さい。部分的に予約制を取り入れることで待ち時間短縮を図っています。
現在、予約にしているのは、
視野検査、メガネ処方、その他特殊な検査、 レーザー治療、外来手術、白内障等の術後1週間以内、数日ごとに頻回の受診が必要な場合
などです。 なぜ毎回視力を測るのでしょうか?
-
視力を測ってみたら気づかないうちに低下していることがあります。
片目だけ視力が低下していても気づきにくいのです。
視力低下には何か原因があるはずです。調べる必要があります。
眼底出血が 発見されたり、視野に異常があったりします。
視力検査をすることで、目の異常を早期発見できるのです。 眼圧は毎回測らなければなりませんか?
-
眼圧が高ければ緑内障の心配があります。
眼圧が少々高くても自覚症状はないので、眼圧の値は測らなければ
わかりません。眼圧は毎日変動しており、また、個人差も大きいので、
繰り返し測定してふだんの眼圧を把握する必要があります。
そして、急に変化した時には原因を調べて対応しなければなりません。
ですから、原則として眼科を受診したときには毎回測定したほうが よいのです。 診察のとき、どこを見ていればいいのでしょう?
-
どこかを見ようとすると、目が動いてしまって、かえってよくありません。
なるべく真っ正面を向いて、右や左に目が寄らないようにして、 ぼんやりしているのがいいでしょう。
目はできるだけ動かさないようにします。片目をつぶるのもよくありません。
両目をあけて、まぶしくても我慢しましょう。
診察用の機械が動きますが、まどわされないようにしましょう。
目を動かすことが必要なときは、医師のほうから声をおかけいたします。 散瞳すると見えづらくなるのですが、どうしても散瞳が必要ですか?
-
眼科では、頻繁に散瞳します。
これは、目薬を使って瞳孔(ひとみ)を開き、網膜や視神経を観察 する検査です。
散瞳しないと、目の奥の細かい点は見えないのです。
強度近視、飛蚊症、白内障、緑内障、糖尿病、高血圧、網膜剥離など、 すべて散瞳が必要です。
検査の重要性をご理解いただき、積極的に この検査を受けていただきたいところです。
散瞳すると、まぶしいですし、ぼやっとして度の合わないメガネをかけている ような感じになります。
5〜6時間くらいで元に戻りますが、個人差が大きく、 元に戻るのに時間がかかることもあります。 目薬をさしたあと、目はあけておくのかつぶるのか?
-
まばたきをすると目薬は涙道から流れていってしまいます。
あまりパチパチとまばたきするのは避けたほうがよいのです。
目をあけたままでまばたきを我慢するのは難しいですから、
目薬をさしたあとは1分くらい目を閉じておくことをお勧めいたします。 目薬をたてつづけにさしてもかまいませんか?
-
2種類以上の目薬が出たときは、5分以上の間隔をあけてさした ほうがよいでしょう。
すぐさしても害になるわけではありませんが、 目薬がどんどん流れてしまってもったいないのです。
もっとも、どうしても忙しい時は、すぐさすのもやむを得ないでしょう。
すぐさしても、半分くらいは残っているそうです。 目薬は冷蔵庫に入れておいたほうがよいですか?
-
はい。私はそう考えています。
目薬を使っていると、まつげにさわったり して細菌が中に入ります。
細菌の増殖を抑えるためには、食品同様、 冷蔵庫で保存することが有効です。
これは「室温保存」の目薬であっても同じです。
>>川本眼科だより55「目薬の保存温度」 目薬はいつまでもちますか?
-
封をあけてから1ヶ月です。
理由は、あまり時間がたつと、中が細菌で 汚染される危険が高くなるためです。
封をあけたジュースを、そんなに長くとっておくことはしませんよね。
ふつう、数日で捨てるはずです。目薬も同じで、一応防腐剤は入っている ものの、それほど高い濃度ではないので、1ヶ月もしたら捨ててしまったほうが安全です。
>>川本眼科だより15「目薬あれこれ」 目薬は寝る直前にさしてはいけないのでしょうか?
-
昔はそういうことが強調されていたようです。
これは、硫酸亜鉛という成分が入っている目薬が多かったせいです。
今では、硫酸亜鉛が入っている目薬はほとんどありません。
(全くないと長い間信じていましたが、調べたら少しは残っているらしい)
今は、寝る前にさしてもさしつかえないと考えてよいでしょう。
むしろ、寝ている時間は長いので、1日4回さす目薬なら1回は寝る前に さすのが普通です。 食事をしていないとき「食後」の薬をのんではいけませんか?
-
ほとんどの場合、食事をしていなくてものんでかまいません。
「食後」になっているのは、胃が荒れないように、という 配慮なのですが、薬の効果と食事とは大して関係ないことが多いのです。
むしろ、十分な効果を得るために1日量を守ることのほうが大切です。
>>川本眼科だより37「薬の服用法」